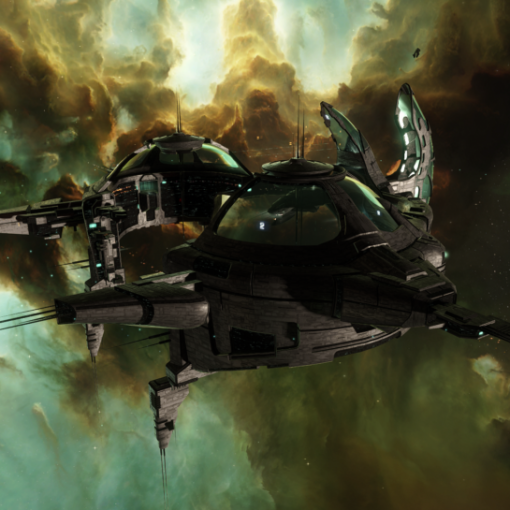この度Saaren Armaの活動に対し、ご援助をいただいたカルダリ人カプセラ「El Shionheart」様の承諾をいただき、ご本人登場のフィクションを書かせていただきました。人物設定などお伺いした上ですが、物語はあくまでもワタシが書いたフィクションですので、ご本人の発言・考え方とは異なっておりますことご了承くださいませ。
for El Shionheart
Flip Slay・Saaren Arma
Trossereに浮かぶステーション。ここはUoC(University of Caille)支部。ステーション内、無機質な通路に沿って各学部の分室が並ぶその一角に、人類学部第7調査班のそれも並んでいる。
第7調査班首席研究員のSaaren Arma(サーレン・アルマ)は分室内の自分の研究室に引きこもって作業に集中していたが、ようやく一段落ついたようだ。
「あぁ……やっと終わったっと……」
ようやく終えた仕事の成果が積まれた机に向かって腰掛けたまま、大きく伸びをするサーレンだが、そこに来客を知らせるブザーが鳴り、若そうな女性の声が響いてきた。
「サーレン、お客様よ。Flip Slayさんがいらっしゃったわ」
この声の主も第7調査班のメンバーだが、今日はエントランスの受付業務を担当してくれている。
サーレンは少し意外そうな顔をしたが、小さく頷いた。
「OK、通してちょうだい」
淡々とした調子でそう答えると、椅子から立ち上がり、もう一度大きく背伸びした。
ワタシは日々、New Eden中を駆け回り、製造業の材料になりそうなものを集めている宇宙庶民ふりっぷ。今日はDodixieに用があったので、ついでに旧友のサーレンの様子でも見ていこうと思って立ち寄ってみたけれど。スピーカーから流れてきた彼女の声はいつも通り淡々としていて、歓迎されているのかどうかよくわからない。まあいいや。
小さな機械音と共に開いたドアから中に入ると、サーレンが机の横に立ってこちらを見ていた。よかった。少なくとも研究に没頭中ではなかったようだ。彼女は喜怒哀楽と、ついでに暴言もストレートにぶつけてくるNaominとは違って、いつも控えめな物腰だが、研究の邪魔をしてしまうと、控えめな物腰のままながらも暴言はぶつけてくる。なんでワタシの周りの女はこうなのだろうか?
そんなことを思いつつ、声をかける。
「やあ、サーレン。調子はどう?」
彼女は少し微笑みを見せつつ机の上の資料を指さした。
「ちょうど今、なかなかやっかいなヤツを片付けたところなの。あなたにしては珍しく、悪いタイミングじゃないわ」
なんでも、ガレンテ民族の歴史を扱った書物の編纂やら翻訳やらが終わったところらしい。まったく何が楽しいのやら……と思っていたら、そんな考えが表情に出てしまっていたようだ。……しまった。
「またあなたは、馬鹿にしてるのね? 人類学は私たち人類がより良い未来を迎えるためにとても重要なことだっていつも言ってるでしょ? 多くの種族が入り乱れるこの世界だからこそそれぞれの種族の今だけじゃなくって過去にも遡ることでそれぞれの類似点や相違点をしっかり踏まえて分析しなくちゃいけないんだっていつも言ってるじゃないだいたいあなたはね……」
いかんいかん、いつも通り興奮して息継ぎがなくなってきた。無理矢理割って入るしかあるまいよ。
「いやー! さすがはサーレンだ! よっ! ジンメイ人の鏡!」
ご高説をぶった切られて不満げな彼女だったが、少し落ち着いたようだ。ひとつ大きなため息をついて、お決まりの捨て台詞。
「ホント、ジンメイ人のオトコはだいたいお気楽すぎると思うのよ……」
ワタシはムダだと知りつつも、こちらもお決まりの反論を言っておく。
「あのさ……すぐにそうやって人種で相手を判断するの、悪いクセだよ?」
彼女はそんなワタシの忠告は完全に無視し、頭を切り替えるように少し散らかった机の上のお片付けに着手する。
「それで、今日は何のご用なの?」
「近くまで来たからさ、ただのご機嫌伺いだよ」
こうしてようやく普段の会話に入ることに成功した。研究モードの彼女を普通の人間に戻すにはこのくらいの前置きが必要なのだ。
ワタシとNaomin――最近はもっぱらなおみん博士と呼んでいるが――そしてこのサーレンは皆、ジンメイ人だ。細かいプロフィールは省略するけれど、ワタシたちは幼なじみというわけではなく、大学で、そう、このUniversity of Cailleで出会ったのだ。もっとも、出会ったのはここのようなステーションではなく、惑星上にある本校だった。皆、カプセラになるつもりなど特になく、普通に地上で暮らす学生だったというわけだ。
その三人のうち、ワタシとなおみんはドロップアウトし、紆余曲折を経てカプセラになり、そして今や個人事業主。サーレンだけは無事に卒業を迎え、そのまま研究者になったのだが、まさか彼女までカプセラになるとは思ってはいなかった。カプセラについてはなかなかに保守的な考え方な彼女だったから、私はそう思っていたのだけれど、さすがリスクをいとわず、文化的な潮流に乗ることに長けると言われるジンメイ人の女性だけのことはあると言うべきか。
ダメだダメだ。サーレンのクセがうつっちゃったよ。
そんなこんなでしばらくの間、他愛もないフレンドトークでムダ時間を消費するワタシたちだった。
「それにしても、サーレン。いっつも言うけどさ。もう少しオシャレに気を遣ったらどうなんだい?」
サーレンはいっつも同じようなTシャツを着て、多少長めの髪の毛も適当に後ろでくくっているだけだ。いくら研究者だからってそこまでステレオタイプな世捨て人っぽくならなくてもいいんじゃないか、とワタシは思うわけですよ。はい。
「放っておいてもらえるかしら? ふりっぷ」
サーレンの声のトーンが少し下がった。痛いところを突かれたからだ。でもこれはいつもと同じやりとりで、いわばお決まりのじゃれ合いのようなもの。こういう遠慮のない言葉をかけることで友情を再確認している……はずだ、たぶん。
だからこのあとの展開もわかっている。このあとサーレンはお金も時間もないのよ! と来て、ワタシはそれは残念、着飾ればもう少しモテるだろうにと返す。そうするとさらにサーレンは反撃に移り……となるはずだったが、ブザーの音が割って入った。そして続けてスピーカーから声が聞こえてきた。
「サーレン、またお客様よ? ……El Shionheart(エル・シオンハート)さんとおっしゃるようだけど……」
さっきワタシが来た時と同じように、受付の彼女が来客を告げるが……そこで急にトーンが下がり、ほとんど内緒話でもするような声になった。
「……あの……カルダリのパイロットスーツを着ているんだけど……通していい?」
そんな言葉にサーレンは一瞬怪訝そうな表情を見せつつ答えた。
「どのようなご用件か伺ってくれるかしら」
そしてほんの少しの空白のあと、再び受付からの音声が入る。
「あの……ごあいさつ……ですって」
うーむ。よくわからない。確かにカプセラはよほど明確に敵対していない限りは各帝国の管轄下にあるステーションへの入港が許可されている。そのあたりは、自由な活動を求めるカプセラと、彼らを都合よく使おうと考える各帝国の思惑が一致してのことだろうが。しかし、UoCは言うまでもなくガレンテを代表する学府であり、そこへ敵国に属するカプセラがステーションに滞在するだけではなく、大学施設にまでやって来るということはあまり聞かない。この何でもありの世界だからこそ、ワタシならお引き取りいただくだろう。でもワタシがそんな助言をするまもなく、サーレンは答えていた。
「わかった、お通しして」
受付との回線が切れると、サーレンは(おい、ちょっとまて)という顔をしているワタシを振り返って言うのだった。
「危ない人だったら守ってちょうだいね?」
もう、帰っちゃおうかと思ったワタシだったけれど、もはや手遅れ。ドアは開かれた。
そこに立っていたのは、紺のパイロットスーツに身を包んだ女性だった。
そのパイロットスーツはすらりとしたスタイルと凜とした立ち姿に妙にマッチしている。セミロングの黒髪も紺色のスーツと溶け合うようなコントラストとなり、落ち着いた雰囲気を演出している。年齢はわからないが、サーレンと並べてみると、これはいわゆる大人のオンナだね。
「ふりっぷ、なにボーッと見ているの?」
サーレンは、だらしなく突っ立ってこの女性を見つめていたワタシを脇に押しやりつつ彼女の前へ進んだ。
「はじめまして、私がサーレン・アルマです。あなたは……えーと」
「エル・シオンハート。お初にお目にかかりますわ。以後お見知りおきを」
「あ……あぁ、シオンハートさんね。私の研究室へようこそ」
サーレンもなかなか冷静な話し方をする方だけれど、ちょっとこの女性が相手だと貫禄負けかな……。なんていうか、大人の余裕っていうのがないんだよな、サーレンには。などと思っていると、なぜかサーレンはこちらに一瞥をよこす。「オマエ殺す」といった視線で。なんでわかるんだ。
「ま……まあ、とりあえずおかけになってください。ご用件はそれから伺いますわ」
「快くお迎えくださって感謝いたしますわ、アルマ……いいえ」
彼女は来客用のソファに腰を下ろしつつ、いったん言葉を切り、言い直した。
「……サーレンと呼んでもよろしいかしら? もちろんわたくしのこともエルと呼んでくださって結構よ。堅苦しいのは得意じゃございませんの」
いや、アンタなかなか堅苦しい口調だよ? そんなことを思っていると今度はシオンハートがこちらに一瞥を。その視線は下等動物を見るが如く。もうイヤだ。たぶん顔に出るタイプなんだろうなぁ。ワタシはもう、鉄仮面を被った置物のように傍らに控えつつ二人の会話を見守ることにしたのだった。
サーレンもローテーブルを挟んだソファに腰を下ろし、シオンハートと向かい合い、話し始めた。
「では、改めて……シオン……いえ、エル、今日はどんなご用件でお越しいただきましたか?」
「わたくし、貴女がいつも発信している各地の調査報告の熱心な読者ですのよ?」
サーレンの表情が和らぐ。
「まあ、読んでくださってるのね、嬉しいわ」
シオンハートはあくまでも上品に微笑み、言葉を続ける。
「もちろんそれに関連して公開なさっている文献の翻訳もチェックしておりますのよ?」
サーレンはなんとか冷静を装おうとするけれど、隠しきれないこの喜びって感じだね。
「コホン……本当に嬉しいわ。だってこれは、学者向けじゃなくてたくさんの人たちに見てもらいたくて始めたことだから。でも、本当に必要とされていることなのかいまいち自信が持てなくて……だから嬉しいの」
やっぱり生の声って嬉しいものだよね。喜びに満ちたサーレンはシオンハートに問いを返す。
「エル、あなたはこういう人類学……とか、歴史とか、そういうのがお好きなの?」
シオンハートは顎のあたりに指をあて、少し考えてから答える。
「もちろん、好きよ……。でも、そうね……好きというより、知りたいっていうのかしら」
彼女はそこで言葉を切ったが、サーレンがじっと彼女を見つめて言葉の続きを待っているのを確認して、さらに続けた。
「様々な星、様々な種族、文化、そして……様々な人間。知らないと損だわ。サーレン、貴女もそうは思わなくって?」
「ええ、そうね。もちろんそう思う。でも、それだけじゃなくって、私は知らなきゃいけないと思うし、研究者として私が知ったことをみんなにも知ってほしいと思う……それはきっと世界を良い方向に……」
シオンハートはしばらく目を閉じ、頷きつつ再びサーレンの瞳をまっすぐに見つめた。
「わたくしもカプセラですから、普段は国や企業から供給される依頼を受けて戦っておりますわ。戦う術さえ知っていれば何も困らないというのが実際のところね。でも、本当の意味で死と隣り合わせではないカプセラだからこそ、色々なことを知っていたい、わかっていたいと……わたくしは、そう思うのよ?」
サーレンははっとしてシオンハートを見つめる。ワタシにもわかるような気がする。カプセラでなければ、宇宙で墜とされるということは死と同義である。だからこそ人は戦いに赴く時には、その覚悟に見合った意義や意味を見いだそうとするのだろう。でも、カプセラは違うのだ。惰性で戦地へ赴き、漫然と戦い続けることができてしまうのだ。不幸なことに。
だからこそ、そんなカプセラが戦う意義を、自分の進む道を見失わずにすむための方法のひとつとして、多くを知るということはとても有効だ。少なくともワタシはそう思うのだ。
サーレンは彼女の言葉に対してしばらく無言だったが、ようやく口を開いた。
「ありがとう、エル」
「ふふ……どういたしまして、サーレン」
それだけのやりとりだったが、見つめ合う二人の視線は間違いなく、互いのことを理解し合った者同士のそれだった。
やがてシオンハートは紙切れを机の上に置き、立ち上がった。
「そろそろおいとましようかしら」
「エル、これは……?」
サーレンは紙切れを手に取り尋ねつつ、そこに書かれた数字に目をやる……やいなやその目は大きく見開かれた。
「ななななにこれ!!」
シオンハートは初めて見せるいたずらっ子のような笑顔で、茶目っ気たっぷりに言ったのだ。
「今どき、紙の小切手なんて洒落てるでしょ?」
「いやいや確かに洒落てるっていうか、あるんだ! 紙の小切手! ……ってちがう! 何この金額!」
「心ばかりの贈りものよ? 少なかったかしら?」
「逆よ逆! こんなの受け取れません! それに寄付っていうことならこれは大学に!」
いつもの冷静なサーレンはどこへ行ってしまったのか。口調が完全になおみん博士のような直情型になっている。でも言ってる内容はやっぱり真面目なサーレンらしい。
「あら、困りましたわね? わたくしはカルダリ人。はっきり申し上げておきますけれど、ガレンテはわたくしにとって敵以外の何者でもありませんの。ガレンテの学校になんて寄付するわけには参りませんわ?」
シオンハートは絶対にまったく困ってないと断言できる口調でそう言った。そんな彼女の紺のパイロットスーツの胸ではカルダリの紋章が誇らしげに室内の照明を受けて煌めいている。
サーレンも受け取れませんとはっきり言った割には小切手を……いや、きっとそこに書かれた金額を食い入るように見つめながら逡巡している。まあ、それほど多くの予算が割り当てられているわけでもなさそうな第7調査班の、首席とは言えまあぶっちゃけ、ただの研究員だからね。気持ちが揺らぐのもわからなくもない。受け取っちゃえよと内心思うけど、いかんせんカタブツなんだよなぁ。そして、そんなサーレンを微笑ましく眺めていたシオンハートは、ふとこちらをに視線を向けた。イヤな予感しかしない。
「そこの置物さん?」
なんで置物設定がばれてるんだ。
「わたくしは、わたくしの望みを満たす研究をしてくださっている、このサーレンに、彼女個人に敬意と親愛を込めてささやかな贈り物をしたいと思っておりますの。個人の尊重……とてもガレンテの流儀に適ったものではございませんこと? わかっていただけますわね?」
残念ながら、まったく逆らえる気がしない。
「あ、はい。わかりますとも……ははは」
「結構。なら、貴方の義務を果たしなさい?」
「がってんです……」
ワタシは小切手を手にオロオロするサーレンの説得を開始した。
それから延々30分。あの手この手を使ってようやくこのカタブツ女を口説き落とすことに成功した。シオンハートは壁にもたれて、ずっと楽しそうに見物していた。見物料としてワタシにも小切手よこせと言いたくなったが、ガマンした。
サーレンは小切手を手に、おずおずとシオンハートに歩み寄った。
「エル、ありがたくいただきます。きっとこれは有意義に……」
シオンハートは最後まで言わせず言葉をかぶせた。
「好きに使ってちょうだいな。もっと良い船を買うっていうのもいいけれど……」
彼女はくるりと背を向けドアの方へ。
ドアは彼女を恭しく迎え入れるようにスムーズに開く。
背を向けたまま手を振りつつ、最後の言葉を。
「サーレン、まずは素敵なお洋服でも買いなさい。置物さん? あなたが見繕ってあげるのよ?」
シオンハートはドアの向こうへ。ドアは閉まる。
サーレンの顔は一瞬で紅くなり、耳まで真っ赤に染まっていた。
ワタシは少しの間、閉じたドアを呆然と見つめていたけれど、やがて気持ちを切り替えて愛すべき友人に声をかけるのだ。
「さあ、Dodixieに服でも買いに行こうか?」
少なくともひとりのカプセラの心を動かした若き研究者、サーレン・アルマ。
彼女は照れているのか、少しムスッとしながらも、ちいさくこくりと頷いた。
おしまい